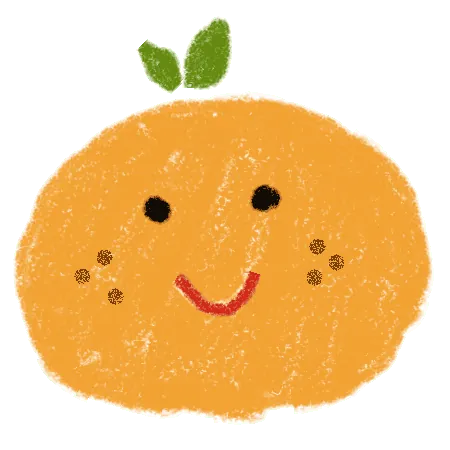1. 【3.2.3つの価値①『コミュニケーション』③】
「コードは未来の自分も他者と同様に読む対象である」という意識に基づき、**心がけるべきこと**はどれか?
解説: 意図が伝わるコードを書くには、構造・命名・コメントの整理が必要である。
補足:意図はできるだけコード内で表現しつつ、Why(設計理由)はコメントや設計メモで補完してよい。
補足:意図はできるだけコード内で表現しつつ、Why(設計理由)はコメントや設計メモで補完してよい。