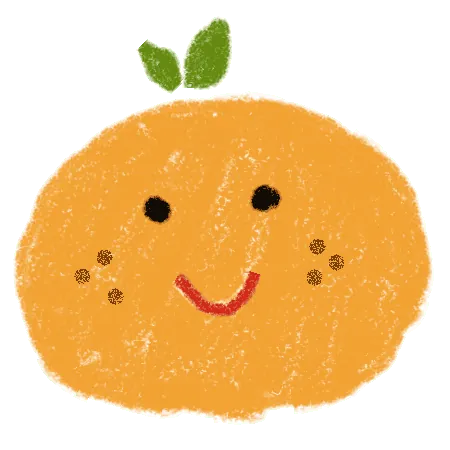1. 【3.39.UNIX思想②『明確性の原則』②】
「明確性の原則」に反するコード例として最も適切なのはどれか?
解説: 1行で複雑な処理を詰め込むと、一見して何をしているのかが分かりにくくなり、「明確性の原則」に反する。

本ページでは、『プリンシプル オブ プログラミング』第3章「UNIX思想」で紹介される、長寿なUNIXを支えてきた17の「シンプルさ」と「小さな部品」の考え方について、要点を押さえた要約と4択クイズで整理します。
要約でUNIX思想の全体像とエッセンスをつかみ → 4択クイズ(10問・全問解説付き)で理解度をチェック → 気になった部分は解説で復習。「読む→解く→わかる」のサイクルで、UNIXの思想を日々のプログラミングや設計にも応用しやすい考え方の軸として身につけていきましょう!
-v)や設定で切り替える※本ページは学習支援を目的とした要約です。実務適用時は原典もご参照ください。
経験:Webアプリ/業務システム
得意:PHP・JavaScript・MySQL・CSS
個人実績:フォーム生成基盤/クイズ学習プラットフォーム 等
詳しいプロフィールはこちら! もちもちみかんのプロフィール