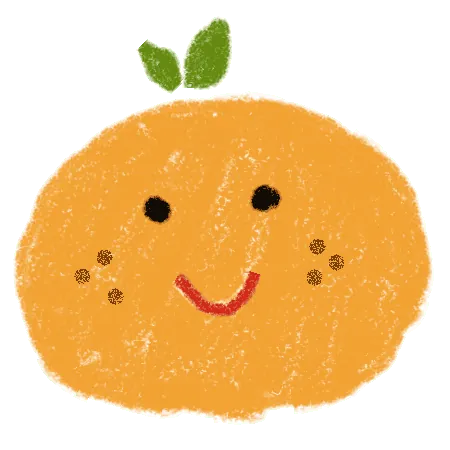1. 【7.4.エントロピーの法則⑥】
「不透明さ」による悪影響として最も適切なのはどれか?
解説: コードが不透明であると、意図が伝わらず保守や修正が困難になる。

本ページでは、『プリンシプル オブ プログラミング』第7章「法則」で紹介される、開発や設計の判断を助ける9つの設計法則について、要点を押さえた要約と4択クイズで整理します。
要約で各法則の狙いと適用シーンをつかみ → 4択クイズ(10問・全問解説付き)で理解度をチェック → 気になった部分は解説で復習。「読む→解く→わかる」のサイクルで、日々の現場で迷ったときに頼れる設計法則を、自分の判断基準として身につけていきましょう!
※本ページは学習支援を目的とした要約です。実務適用時は原典もご参照ください。
経験:Webアプリ/業務システム
得意:PHP・JavaScript・MySQL・CSS
個人実績:フォーム生成基盤/クイズ学習プラットフォーム 等
詳しいプロフィールはこちら! もちもちみかんのプロフィール