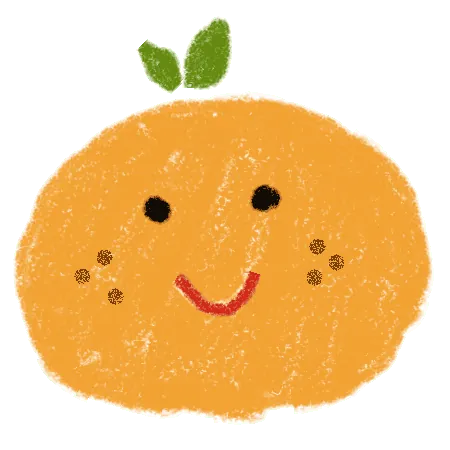1.1 プログラミングに銀の弾丸はない(No Silver Bullet)
要旨一発で全部解決する“魔法の方法”はない。ソフトウェアはそもそも複雑。
結論歴史に学び、小さな改善を積み重ねよう。道具や設計のムダ(偶有的な複雑さ)は減らして本質に集中する。

本書『プリンシプル オブ プログラミング』に凝縮された101の原理・原則を、効率的に、かつ深く理解するための「総合ナビゲーション」ページです。
最高のコードを書くための「3つの前提」「7つの設計原則」「6つの実践テクニック」をまずは一望。その上で、全101の原則の要点解説と、合計736問(演習674問+コードレビュー演習62問)という圧倒的なボリュームを誇るクイズ、さらに用語集・章別まとめへのリンクを体系的に整理しました。
各章の詳細解説にもすぐアクセスできるため、あなたの「学習のスタート地点」として活用してください。
『プリンシプル オブ プログラミング』は、プログラミングにおける設計原則などを 7章・101の原理・原則にまとめた本で、本書が目指す 「最高のコード」とは、次の4つを満たすことだと位置づけています。
本書では、前提・原則・思想・視点・習慣・手法・法則という7つの切り口で101の原理・原則を整理していますが、 このページではその中でも、毎日のコーディングに一番直結する 「3つの前提」「7つの設計原則」「6つの実践テクニック」にフォーカスします。
まずはここを押さえるだけで、「このコードの書き方でいいかな?」という迷いに対して、 共通のものさしを持って判断できるようになります。そのエッセンスを1分でつかめるようにギュッと凝縮しています。
どんな技術にも魔法はなく、地道な設計の積み重ねが必要。
最終的に読まれるのはコードだけ。設計の意図はコードに表現する。
要件も環境も変わる前提で、変更しやすい構造にしておく。
できるだけシンプルに、余計な複雑さを持ち込まない。
同じ知識を重複させず、1か所を直せば全体が整うようにする。
いつか使うかも、で作らない。本当に必要になってから実装する。
意図をはっきり持ち、その意図が伝わるようにコードで表現する。
関数内で扱う抽象度のレベルを揃える。
変更ではなく「拡張」で対応できる構造にしておく。
役割が一目で分かる名前を付ける。いい名前は最高のコメント。
細く速い“試し撃ち”で全体の通り道を先に確認する。
前提条件・戻り値などの「約束」を明確にして設計する。
想定外の入力や状態を常に疑い、早めに検知して安全側に倒す。
自分たちで自分たちのソフトを使い、使い勝手や問題を体験する。
誰か(ダック)に説明するつもりでコードの意図を言語化し、バグや違和感を見つける。
どんな状況・背景のもとで使われるコードかを踏まえて、最適な設計を選ぶ。
章フィルタ
全101の原理・原則を表示しています。
要旨一発で全部解決する“魔法の方法”はない。ソフトウェアはそもそも複雑。
結論歴史に学び、小さな改善を積み重ねよう。道具や設計のムダ(偶有的な複雑さ)は減らして本質に集中する。
要旨一度書いて終わりではない。要件変更や修正で、コードは必ず更新される。
要旨まずは“シンプル”。動かすための最小限だけ作り、余計なことはしない。
結論最小構成で作って、複雑さを足さない。新技術の無理な導入や「今いらない機能」は避ける。
要旨同じことを何度も書かない。コードもコメントも重複はバグのもと。
要旨「多分必要」はたいてい不要。今必要なものだけを作る。
結論将来のための作り込みはしない。必要になった時に、その時の最適解で足す。シンプルさは結果的に変更に強い。
要旨コードは人が読む。意図が伝わるように、はっきり・分かりやすく書く。
結論読みやすさ最優先。命名・分割・整った構造で誤解を減らし、Why(設計理由)はコメントやドキュメントで補う。
要旨関数やブロックの“抽象度”を揃えて書くと、読みやすくなる。
結論上位は下位だけを呼ぶように分割し、横刺しや逆流を避ける。文書の目次のように構造を整える。
要旨コードは“拡張に開き、既存修正には閉じる”ように設計する。
要旨命名はソフトの“UI”。分かる名前はバグも手戻りも減らす。
結論仕様理解を深めたうえで命名し、実装と照らして常に見直す。ドメイン語彙で一貫性と具体性を保つ。
リンク:
要旨良いコード=拡張しやすく、ムダがなく、読みやすく、理解しやすい。これを支える考え方が「セオリー」。
結論3つの価値(伝わる・シンプル・柔軟)を土台に、6つの原則を道しるべにして、具体のコードへ落とし込む。
要旨コードは人に見せるドキュメント。読み手(未来の自分を含む)が分かることが最重要。
要旨シンプル=余分な複雑さを除いた状態。ムダは不具合や読みづらさの原因になる。
要旨柔軟性=変更しやすさ。コードは必ず変わる前提で備える。
要旨変更の影響が広がらず、特定の場所に閉じるように設計する。
結論責務と境界を明確にして近接配置。変更は特定モジュールで完結できる構造にする。
要旨重複は不整合やテスト漏れを招く。1か所を直せば全体が更新される構造にする。
要旨処理とその対象データを近くに置くと、変更が楽で齟齬も減る。
結論データの近くに振る舞いを置く(カプセル化)。境界でデータを変換してから処理する。
要旨同じ種類のものは同じ表現にそろえると、予測しやすく読みやすい。
要旨「同じ理由・タイミングで変わるもの」は同じ場所に集めると強い。
結論単一責任の原則に沿って配置。変わりやすい部分は分離し、境界で隔離して影響を小さくする。
要旨良いコードを支える共通の基礎原理をチームで共有し、設計判断のブレを無くす。
結論プロダクト横断のチェックリスト化して、日々の設計・レビューで使う。
リンク:
要旨概念に線を引き、何を扱い何を捨てるかを決めてモジュールを区別する。
要旨関連するデータとロジックをひとつのモジュールに包み、外部からの混入を防ぐ。
要旨内部の詳細は隠し、外からは最小のインターフェースだけを見せる。
結論公開は必要最小限。利用者に必要な情報のみを提供し、実装詳細は隠す。
要旨関連モジュールを意味単位で束ね、全体を分かりやすい塊にする。
結論関連性を見てボトムアップで集合化。進行に合わせて構成を育てていく。
要旨機能や目的ごとにコードを分け、互いを独立させる。
結論異なる責務は分割(例:UI/DB/制御)。横断的関心事はAOP等で切り出す。
要旨抽象は十分で漏れなく、操作は原子的であるべき。
結論提供関数を見直し、十分・完全・純粋な最小セットに整える。余計は削除か分離。
要旨変わりやすい方針(ポリシー)と安定しやすい実装を同居させない。
要旨使い方の契約(インターフェース)と中身(実装)を分け、利用側は契約だけに依存する。
結論「インターフェースに対してプログラムする」を徹底し、直接実装を呼ばない。
要旨宣言・定義は一度きりにし、再代入や共有可変状態を減らす。
結論参照透過な関数と不変データ中心へ。副作用を抑え検証しやすくする。
要旨大きな問題は小さく分けて、それぞれ解決してから統合する。
結論責任・データ・計算の単位で境界を引き、小さくして各個撃破する。
要旨機能以外の品質(非機能)は、運用・保守・拡張のコストとリスクを左右する最重要領域。
結論要件定義→設計→テストの各段で非機能の基準を明確化し、構造で満たす設計を徹底する。
リンク:
要旨素早く安全に修正・拡張・再構成・移植できる力。
要旨他システムと機能/データをやり取りできる能力。
結論契約ベースのAPIと標準プロトコル/データ形式を採用し、スキーマとバージョニングを管理する。
要旨限られたリソースで必要な性能を出す(時間効率+資源効率)。
要旨例外や誤操作、異常時でも機能を保つ力(フォールトトレランス+ロバストネス)。
要旨効果的・効率的に検証できる構造かどうか。
要旨再利用される/する双方で価値を高め、「作らないこと」で品質と速度を上げる。
結論“3の法則”を目安に汎用化し、API安定化・ドキュメント・バージョニングで採用性を高める。
要旨障害を作り込まないための7つの観点を共通言語にし、設計とレビューの軸をそろえる。
要旨常にシンプルを選び、見通しの良い自然なコードを書く。
結論高等テクより「単純・直截・最小」。まず動く最小で止め、複雑化はそれが必要だと言う根拠が出たときだけ。
要旨同じことは同じ形で表現し、コードの一貫性を保つ。
結論スタイル/命名/構造/パターンを統一。似た処理はシグネチャや戻り値、例外方針もそろえる。
要旨対称(対)を意識して設計すると、予測しやすく読みやすい。
結論条件には反条件、操作には逆操作を用意。対称が崩れるなら要件から見直す。
要旨階層構造で編成し、上位→下位の主従関係を明確にする。
結論大→中→小の秩序で構造化し、上位は下位を外部視点で扱う。横刺しや逆流の依存は避ける。
要旨処理はできる限り直線的に。分岐と状態は最小にする。
結論ガード節で早期return、複雑条件は述語化/表引き、必要なら明示的ステートで管理する。
要旨一見して正しいと分かる明瞭なロジックを書く。
結論単機能関数・一文一義・意味のある命名。Why/契約/前後条件をコードやコメント、図で明示する。
要旨想定外も起こる前提で、安全側に倒す設計・実装を行う。
結論else/default/セーフガード必須。フェールセーフ/ソフト/FTを織り込み、リトライやRBを設計判断で使い分ける。
要旨長年の実践から生まれた設計・実装の技法群で、今も通用する普遍的な指針。
要旨関係の強い要素をひとまとまりにして最小のインターフェースに削る。
要旨巧妙さより明確さ。人が一目で理解できるコードにする。
結論意図が伝わる命名・整形・コメントを徹底し、推測を要する書き方を排除する。
要旨入出力をテキスト/JSONなどのストリームで扱い、部品同士をつなげやすくする。
要旨設計・実装は常にシンプル最優先。複雑さは自然に増えるため自制が必要。
結論「Less is more」を合言葉に最小構成でデプロイ。足す前に削るを検討する。
要旨大きさ(量と複雑さ)を避け、小さく作る。
要旨外から挙動が理解でき、内部状態も観測できる設計にする。
要旨透明・単純な内部構造で、異常や入力変動に強い実装を保つ。
結論作者が説明できる構造を維持。特異/極端入力でストレステストし、安定性を常時確認する。
要旨ロジックではなくデータで表現する(テーブル/設定駆動)。
結論既存の慣習・用語・挙動に合わせ、一貫性を保つ。似て非なる挙動は避ける。
要旨出力は最小限にして重要情報だけを見せる。
結論本当のエラーのみ標準エラーへ。詳細はverbose切替で提供し、デフォルトはサイレントに。
要旨回復できないエラーは早期に大きく失敗させ、発見を容易にする。
要旨最も高価なのは開発者の時間。環境投資は最終的にコスト削減に効く。
結論良いハード/ツール/情報アクセスに投資し、待ち時間や手作業のボトルネックを除去する。
要旨コードを生むコード(生成/テンプレ/AI)を活用して反復を自動化する。
要旨速さより正しさ。最適化は計測に基づいて段階的に行う。
結論必要性の証明→計測→改善→再計測。削除は最大の最適化であることも忘れない。
要旨唯一の正解はない。選択肢を持ち、文脈で選ぶ。
結論断定を避け複数案を比較検証。言語/フレームワーク/配置/プロセスの多様性を前提に意思決定を記録する。
要旨将来の拡張を前提に、後方互換を保ちながら差し替え/追加できる構造にする。
要旨入力は寛容に、出力は厳格に。ただし「寛容」は仕様解釈ではなく動作で行う。
結論入力は検証・正規化して受容、出力は規格に忠実に整形。互換テストを自動化し、仕様解釈は厳密に保つ。
要旨UNIXの長寿を支えた設計の哲学を、現代開発の指針として活かす。
結論小さく作る/一仕事に集中/早い試作/移植性重視/テキスト志向/組み合わせ活用を日常の設計・実装に適用する。
要旨ソフトは小さいほど理解しやすく、保守しやすく、組み合わせやすい。
結論小さく始めて小さく保つ。追加は必要が証明された最小限に(Less is more)。
結論関心を分離し、1文1処理で本質を明確に。
要旨早く作って見せれば、誤りや不足を早期に潰せる。
結論早期プロト→短サイクル改善→段階リリースで最適点に収束させる。
要旨長い目では移植性の方が価値を生むことが多い。
要旨テキスト(今ならJSON等)は最も扱いやすくポータブル。
結論独自バイナリは最小限にし、標準的なテキスト形式を優先する。
要旨良い部品を組み合わせ、他者の成果を「てこ」にする。
結論単機能ツール+グルー言語で大仕事を成す。内製は核に集中する。
要旨過度な対話UIは学習・連携・自動化の足かせになりやすい。
結論基本は非対話(CLI/設定/ファイルI/O)。必要なら初心者UIと非対話の両方を用意。
要旨すべてのプログラムを「受けて加工して出す」直列可能な部品にする。
要旨日々の細部判断を支える軽量ルール集で、UNIX的実用主義を徹底する。
結論環境カスタマイズ/小さなカーネル/小文字命名/紙依存排除/沈黙/並列思考/部品連携/90%解/最小公約数重視/階層指向をチームの共通ルールにする。
要旨1つのモジュールの中身が「同じ目的」にどれだけ集中しているかの度合い。高いほど良い。
結論目標は「機能的強度」=1モジュール1役割。責務をはっきり決めて、関係ない処理を入れない。
要旨モジュールどうしのつながりの強さ。弱いほど変更の影響が広がらず安全。
結論目標はデータ結合。必要最小の引数でやり取りし、グローバルや制御フラグ依存を避ける。
要旨部品同士を独立させ、片方の変更がもう片方に波及しない状態を作る考え方。
要旨あとで戻せる設計にしておく発想。不可逆な選択は避ける。
結論技術や前提に縛られすぎないよう、間接化や独立モジュール化で「やり直し可能」を確保する。
要旨読みづらい・直しづらい前ぶれサインのこと。見つけたら小さく安全に直す。
結論重複はまとめる/長い・大きいは分割/不要な仲介は削除/名前は実態に合わせて即修正する。
要旨急ぐために残した粗い実装は「借金」。放置すると利息(手戻り・遅さ)になる。
結論やむなく負債を取るなら内容・影響・返済期限を見える化し、テストで守りつつ速やかに返済する。
要旨怠惰・短気・傲慢を「仕組み化・自動化・プロ意識」に変えて、無駄と手戻りを減らす。
結論面倒はツール化し、コンピューターに任せ、胸を張れるコードを作る。長時間労働で解決しようとしない。
要旨触れたコードは「来たときより少しきれい」に直して戻す。
要旨時期尚早な最適化は害。まずは変更を局所化できる「良い設計とコード」。最適化は必要時のみ計測に基づいて。
結論必要性を証明→計測→ボトルネックだけ直す→再計測。可読性や移植性を犠牲にしない。
要旨人ではなくコードを批評。指摘を歓迎し学ぶ姿勢で品質を上げる。
結論謙虚さと尊重を持ち、十戒を意識。相談なしの全面書き直しは避け、バランスよく継続改善する。
要旨小さな作業を1つずつ進め、確認→次へを繰り返すと品質も速度も上がる。
結論結論を急がず段階を刻む。考えを記録し、直感は試しつつも検証で決める。
要旨やり方は1つではない。文脈に合う選択肢を比較して選ぶ。
結論評価基準を明確にし、複数案を検討・試作。よりシンプルで持続可能な方法を選ぶ。
要旨まず最小でも実環境で動く“骨格”を通し、学びと調整のサイクルを早める。
結論本物の最小コードで端から端まで動かし、以後は肉付けしつつ狙いとの差を常時修正する。
要旨呼び手と受け手で「前提条件・事後条件」を合意し、その契約どおりに実装する。
結論仕様はコメントで明示し、アサーションで契約を検証。前提を満たさず呼ばない/満たせないなら早期に失敗させる。
要旨「かもしれない」を前提に、入力と境界を徹底チェックして被害を最小化する。
結論入口で検証→内部はクリーンに。想定外はアサートで即検出、想定内は方針に従って安全に処理する。
要旨自分のソフトを自分で使い、ユーザー視点の欠点や不便をあぶり出す。
結論実環境・実データで正常系も異常系も操作し、体験のギャップを発見して優先度をつけて直す。
要旨問題を順序立てて“誰か”に説明すると、矛盾や見落としに自分で気づける。
結論再現手順→期待→現状→差分→仮説の順に声に出して説明し、最小再現へ縮めていく。
要旨背景・状況(文脈)を設計・実装・会話に組み込み、判断の質を上げる。
結論ドメインモデルで文脈を共有し、階層化・驚き最小でコードに反映。中断を減らし、全体最適の視点で決める。
リンク:
要旨炎上中に人を足しても、教育や調整が増え、むしろ遅くなる。
結論人海戦術に逃げず、早めに計画を組み直し、優先度を付けて段階的に出す。
要旨設計は組織構造の写し鏡になりやすい。
結論理想のアーキテクチャに合わせてチーム編成を組み、境界を一致させる。
リンク:
要旨小さな乱れの放置が、全体の劣化を加速させる。
結論気づいたらすぐ直す。時間がなければタグで可視化し、必ず後で修復する。
要旨コードは放っておくと必ず乱れていく。
結論小さなリファクタリングとテストを継続し、腐敗の兆候を常に監視して戻す。
リンク:
要旨多くの要求はすぐ満たせるが、残りはコスト高 or 実現困難になりがち。
結論100%に固執せず、重要な少数に集中。ホットスポットを計測して手当てする。
要旨名前を付けると現象が見えるようになる。
結論概念に良い名前を与え、用語をチームで統一して認知と共有を加速する。
要旨v2で機能を盛りすぎ、重く使いにくくなりやすい。
要旨既存で足りるのに同等機能を自作してしまう。
結論着手前に標準/OSSを調査し相談。自作は差別化の核や学習目的に限定する。
要旨前提タスクに追われ、本来の目的を見失う連鎖。
結論目的と制約を明文化し、逸脱に気づいたら停止→相談→別ルートを検討する。
※本ページは学習支援を目的とした要約です。実務適用時は原典もご参照ください。
本クイズは、プログラミングおよびソフトウェア設計に関する理解を深めることを目的として作成されたものであり、正確性・完全性・最新性を保証するものではありません。
本クイズの内容は、一般的な設計原則や哲学的背景に基づいて構成されていますが、すべての現場や状況に適用できるとは限りません。
出題内容や解答・解説において、誤りや誤解を招く表現が含まれている可能性があります。あらかじめご了承ください。
本クイズの利用により生じたいかなる損害・損失についても、当方は一切の責任を負いかねます。
問題文・選択肢・解説の内容は予告なく変更・更新される場合があります。
教育・学習・社内研修などに利用される場合は、各自の判断と責任のもとでご活用ください。
経験:Webアプリ/業務システム
得意:PHP・JavaScript・MySQL・CSS
個人実績:フォーム生成基盤/クイズ学習プラットフォーム 等
詳しいプロフィールはこちら! もちもちみかんのプロフィール